滋賀男声合唱団
Que tout l'enfer fuie au son de notre voix...
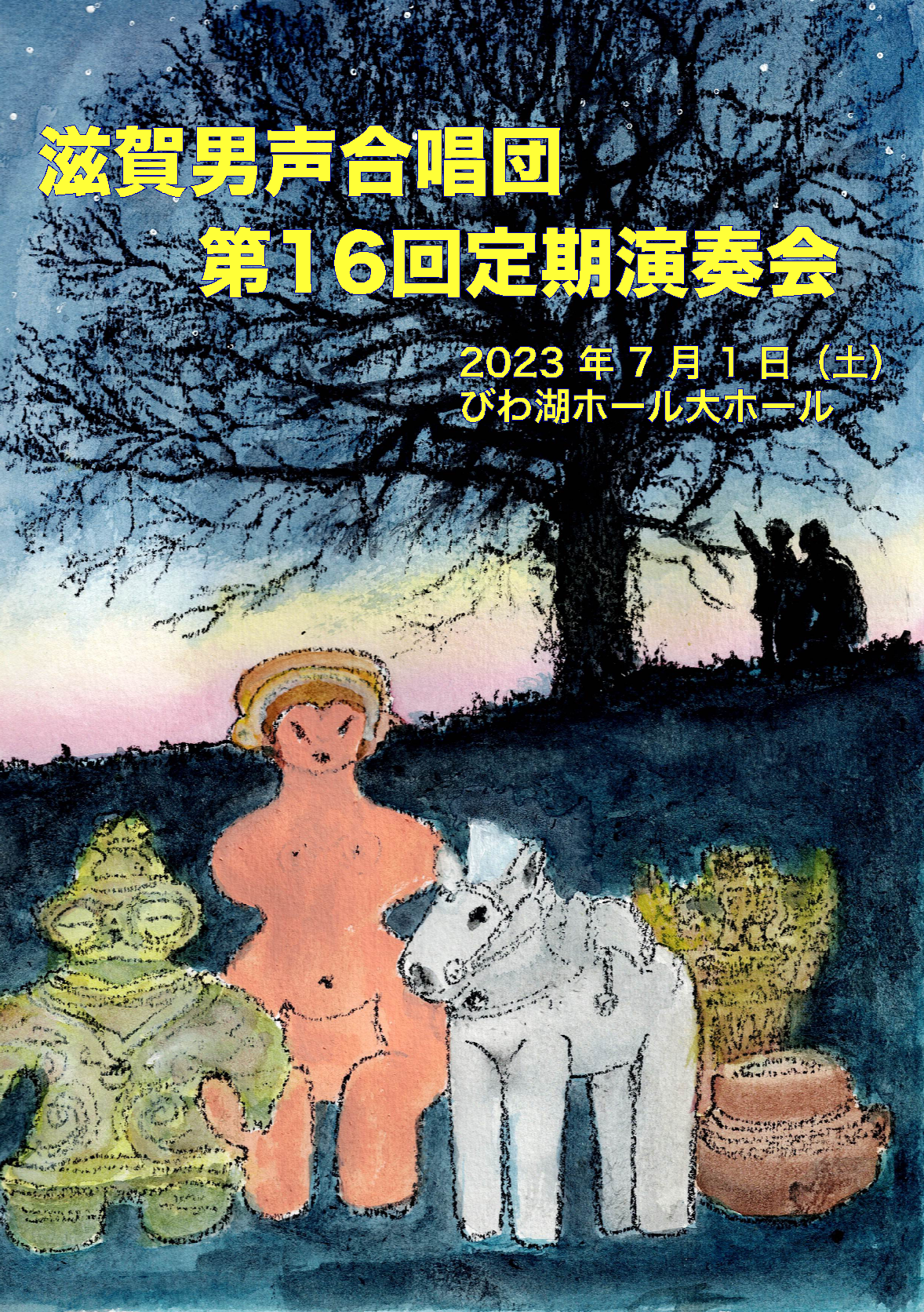
Que tout l'enfer fuie au son de notre voix...
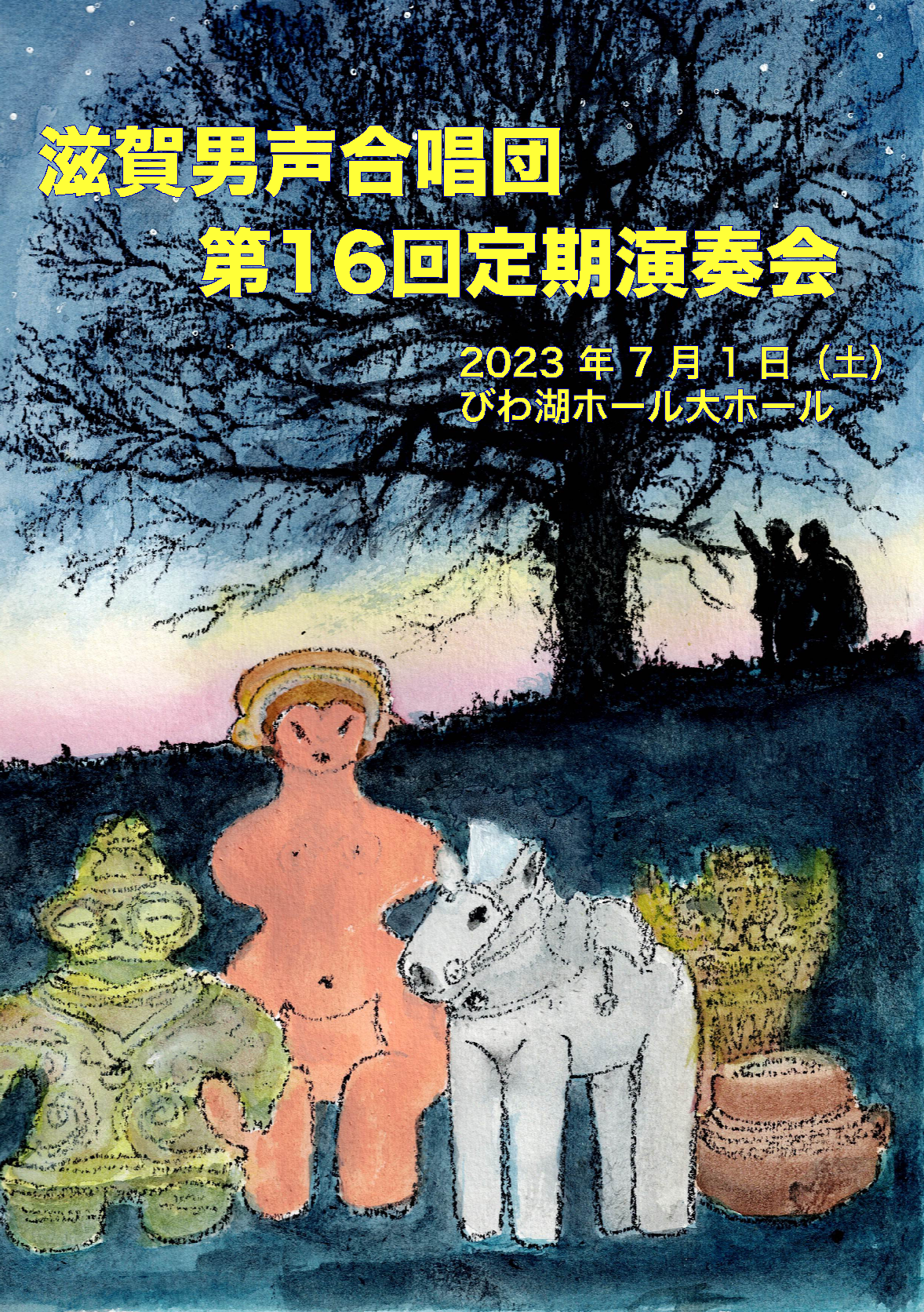
私が学生のころ、《水のいのち》を歌えなければ合唱人じゃないと言われるほど、日本中の合唱団によ って演奏されていました。昭和 100 年のいま、当時は気づかなかった新たな視点を得て、この曲を多く のワンステージメンバーのご参集と共に演奏できることを心から嬉しく思います。
熱心なキリスト者であった髙田三郎先生。氏は旧約聖書「創世記」の記述から、《水のいのち》の作曲 の着想を得たのではないか──そんな思いが私の中でふつふつと湧いてきました。冒頭に「初めに神が天 と地を創造された」とあります。「地」と聞くと私たちは陸地を思い浮かべますが、「水に覆われた混沌と した地」を神は創造されたのです。天地創造を「混沌から秩序への移行」ととらえるならば、神はまず 「天」と「水で覆われた地」に光をもたらし、大空を設け、水を分け、陸地を現し、さらに生命を宿らせ ていかれた──まさに、カオスをコスモス(秩序ある世界)へと変えていく流れなのです。この解釈は、 人間の霊的成長や人生にも当てはめることができるでしょう。混沌とした状況や試練の中でも、神がそこ に秩序を与え、新しい形を生み出してくださる──そう考えると、天地創造は単なる過去の物語ではな く、今を生きる私たちにとっても示唆深いものとなります。
———各楽章と天地創造の関係———
第 1 曲「雨」 —天の水の恵みと秩序のはじまり(創世記 1:6-7)—
天地創造の過程で「水」は秩序を得て、大空の上と下に分かれます。雨はその循環の一部であり、神がもたらす恵みの象徴です。混沌から秩序を生み出す主の愛の目的の始まりです。
第 2 曲「水たまり」 —小さな水の中に映る宇宙と生命の芽生え(創世記 1:9-12)—
水たまりという小さな世界の中に、宇宙が映り込み、生命の兆しを覚えます。「小さな水たまり」に映り込む自己と向き合うような感覚を生み出しています。
第 3 曲「川」—神の導きと生命の流れ(創世記 2:10)—
「エデンの園を潤す川」と「ノアの大洪水」のイメージが重なります。川もまた生命の源であり、また神が定めた秩序に従い、時にしずかに、時に神の怒りを伴う流れとなります。
第 4 曲「海」—水の包容力と創造の完成(創世記 1:10)—
海はすべての水が行きつく場所であり、包容力を持つ存在として描かれます。創世記1:10では、神が「水の集まる所を海と呼ばれた」とあり、ここに初めて海が明確に創造されます。
第 5 曲「海よ」—神の永遠の創造と循環(創世記 1:31)—
水が単なる自然の一部ではなく、命を育む根源的な存在として歌われます。創世記の「すべてを神が良しとされた」(1:31)という創造の完成を象徴し、組曲の締めくくりとなっています。
———バプテスマ(洗礼)との関連———
「混沌から秩序への変化」としての水の象徴性に加えて、「海」をテーマにした第 4 曲と第 5 曲では「水に沈むこと=死」「水から上がること=復活」、すなわち神の赦しと新しい命を授かる「バプテスマ(洗礼)」の象徴と読み解くことができます。天地創造の創造主の目的を含みつつ、バプテスマを通して新しい命が与えられ、蘇るプロセスを描いた作品としても解釈できるとの気づきを得ました。
———感謝を込めて———
髙田三郎先生の奥様、留奈子先生はご生前、私に「もし主人が生きていたら、富岡さんとの出会いをどれだけ喜んだことでしょう」と。私の心に深く刻まれたうれしいお言葉です。この曲の男声合唱版の初演指揮者・日下部吉彦先生は、ご生前は滋賀男声の演奏会に必ずお出ましくださり、私たちの活動を見守って下さいました。このお二人のお支えと励ましに感謝を込めて、今回の演奏に臨みます。

Made in RapidWeaver